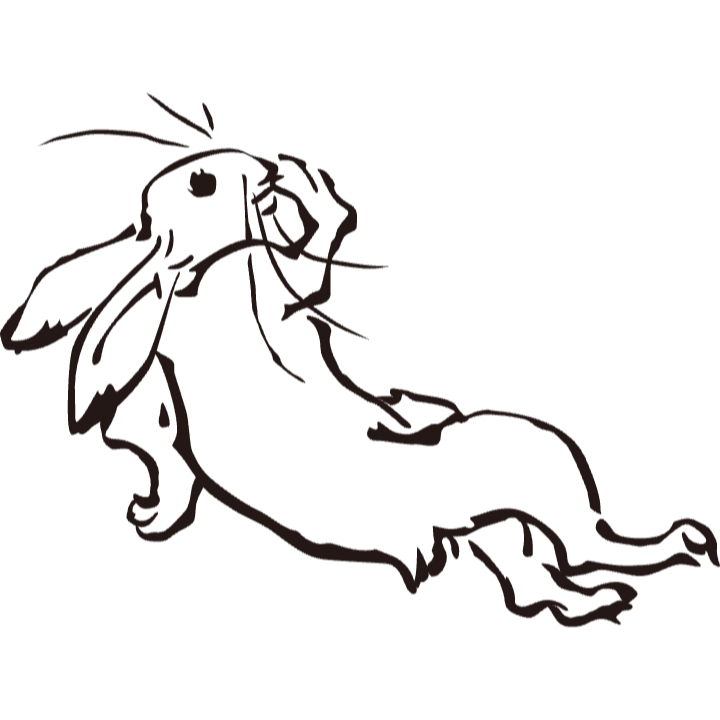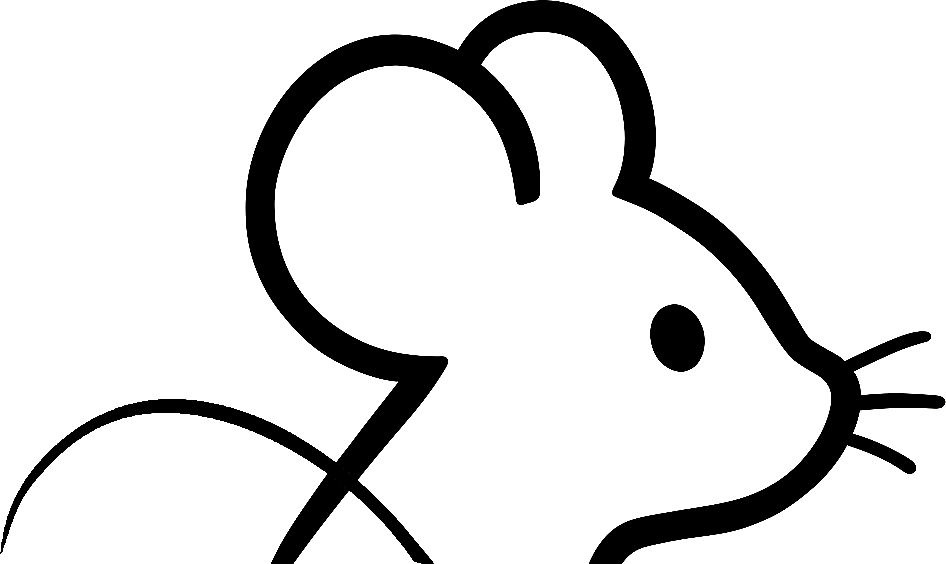
しても死なない
あなたは今、プラットフォームにのせられていませんか。プラットフォームというのは、だれかの用意した仕組みのこと、一種の「テクノロジー」のことです。それはたとえば、ソーシャルメディアのような場所にかぎった話ではありません。学校や企業、工場もそう。社会保障や税制をはじめとする制度も、広い意味でのプラットフォームです。
ともすると私たちは、そこから不本意におちてしまうことがあります。しかしむしろ、勇気をだしておりてみたとしたら、どうなるでしょうか。もしかすると、そこには本当の意味でのゆたかで自由な世界がひろがっているかもしれません。Orillo はそろそろとおりた先で地に足をつけて歩きはじめるための運動です。
[名] orillo /オリヨ/:
縁(ふち、へり)、際(きわ)、端(はし)、傍(そば、かたわら)
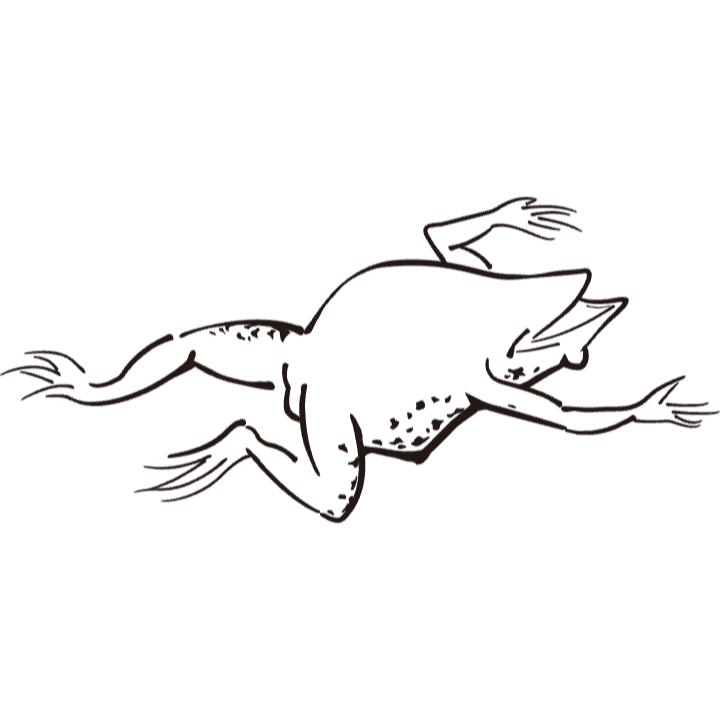
プラットフォームの何が問題なのか
プラットフォームは、人を囲いこみ、それなしでは生きられなくさせようとします。そのようなロックインのために、さまざまな仕掛けをこらします。
- まず、プラットフォームは、生の営みをブラックボックス化することで、人が自立する力を奪います。その典型が工場制手工業です。大量生産のために作業工程が分割され、別々のタスクが労働者に割りあてられます。その結果、人がひとりで生きる技術を身につけたり周囲と連携することが困難になります。
- 次に、ネットワーク効果を利用します。ネットワーク効果とは、プラットフォームの規模が拡大する分だけロックインが強化されるという現象です。その典型がメッセージや決済のサービス、SNSといったものです。大きな質量のものがそれだけ強い重力を持つように、みんなが使っているから自分も使うしかなくなる、ということがしばしば起きます。
また、プラットフォームの成功は、しばしば劣化 enshitificaiton を招きます。プラットフォームはロックインによって寡占状態を確立すると、運営側の利益を最大化するために、サービスの利用者や被雇用者を積極的に収奪するようになります。たとえば、SNSにおいては、広告を増やすなどしてユーザー体験を悪化させた上で、改善と引きかえに月々の使用料を徴収するといったことが考えられます。
さらに、現代において、プラットフォームはデータコロニアリズムの装置にもなています。企業や国家は最大限の利益を追求するなかで個人情報を最大限に収奪しようとします。収奪の対象になるのは、個人情報だけではなく、私たちの人間的なつながり、社会生活までを含みます。特にSNSや検索エンジン、AIとのやりとりにおいては、私たちが何気なくそれを使うだけでプラットフォームへの無償の奉仕をさせられるような状況があります。それをデジタル労働といいます。
Orillo の目指すこと
プラットフォームは私たちを孤立させ、家畜のように従順な存在にした上で、システムの維持のための養分として使い潰してきました。すでにそのような現状が深刻化するなか、既存の囲いから完全に抜けだすということ、つまりある種の野生に還ることは、とても難しいことです。そこで、Orillo が目指すのは、家畜でもなく、野生でもない、野良状態の模索です。プラットフォームを活用しながらも、魂までは売り渡さないでおくこと。いざというときに、それなしでも生きられるようにしておくこと。そのようなライフスタイルを文化的にも経済的にも実践すること。では、具体的には、そのために何ができるでしょうか。いくつか例を挙げてみます。
文化的な実践⎯⎯デジタルライフの見直し
日常のデジタル化にともない、普段どんなツールをどんなふうに利用しているかなど、私たちの具体的な生のあり方が他人からは不可視のものになるとともに、私たち自身も視野狭窄に陥ります。その結果、さまざまな問題が生じることになります。
たとえば、そのひとつが私たちのデジタルホームレス化です。デジタルホームレス化とは、私たちのアイデンティティを構成するようなデータ(たとえば、X や note といったウェブサイトでの発言)や人間関係をプラットフォームに明け渡しているような状態のこと。つまり、データポータビリティが認められておらず、それまでの自分自身の歴史がプラットフォームと不可分になっている状態のことです。
このようなプラットフォームへの隷属状態を避けるための動き、個々人のデータ主権を守る動きがさまざまな言語圏で行われています。たとえば、indieweb.org という運動には、POSSE(Publish on your Own Site, Syndicate Elsewhere)のすすめというものがあります。これは、自分の拠点となる個人のウェブサイトにデータを集約した上でそれをほかのプラットフォームに分散配信する、という考え方です。
あるいは、個々人のメッセージのやりとりにおいて、営利目的で開発されたアプリではなく、オープンソースのプロトコルを重視する動きもあります。一例として、既存のメールプロトコル(IMAPやIMAP)を用いたdelta.chat のようなチャットアプリや Matrix Protocol が挙げられますが、これは LINE や Telegram、Discord といったアプリの有効な代替案になることでしょう。
経済的な実践⎯⎯労働力の安売りをしない
企業は、典型的なプラットフォームです。一般論として、労働市場からできるだけ安価に仕入れた労働力から最大限の利益を得ることを目指します。それを搾取といいます。企業は効果的な搾取のため、雇われることなくしては生きてはいけないような「ゆとり」のない状態に私たちを陥れようとします。しかし、賃労働をしなければ死ぬ、という考え方は、プラットフォームにとって都合のいい神話にすぎません(労働の欠如によって死ぬことになるのはプラットフォームのほうです)。
現代の日本において、個人事業や合同会社を立ちあげることは、一般に考えられているよりもはるかに容易にできます。仮に赤字経営になったとしても、公的扶助制度を利用することで最低限の文化的な生活を送ることも可能です。その一方で、現実問題として大多数の人がプラットフォームの中にロックインされている以上、賃労働に携わらないことによって周囲から孤立するということは充分に考えられます。
Orillo はそこで、賃労働によらずに生きる人々のつながりの構築を目指します。そのなかには何らかの形で不労所得がある人やない人、主夫(主婦)をはじめとする家事・感情労働者も含みます。現在「自立支援」という日本語は、「社会復帰」のような言葉と同様、囲いの外にいる者を内側に回収するという意味合いで使われることが多いです。しかし、自立とは本来、囲いの外にあるものなのではないでしょうか。本当の社会もまた、囲いの外にあるはずです。
Orillo のこれから
Orillo は、2025年4月に立ちあがったばかりの運動です。法人化を視野に入れながら、三つの柱を立てて活動をしていきます。
- メディアの立ちあげ:脱プラットフォームをめぐる情報の発信
- コミュニティの運営:掲示板やメーリングリストの運営
- 自立支援:脱プラットフォームのための文化・経済的な支援
詳しい情報は、下記のプロトコルを通して配信しています。
- Mail:mail-join@orillo.org(空メールを送信)
- RSS:orillo.org/feed
- Activity Pub:orillo@orillo.org
- AT Protocol:bsky.app/profile/orillo.org
- Matrix:orillo:matrix.org
Orillo にかかわる
よろしければ、いっしょに Orillo を作っていきませんか。現在賃労働中の方を含め、Orillo と志を同じくする方であれば、どなたでも大歓迎です。特別な技能も要りません。年齢や国籍といったものも問いません。下記の連絡先までご一報ください。